
正直、虫が一番怖かった
事実関係・疑問点の整理:アイリーンの力とヴァラクとの“関係”
明かされたアイリーンの秘密
●アイデンティティの確立
アイリーンの母は「異端者」として強制入院させられた。アイリーンもその母に似て「普通と違うから」と追い払われ、修道院へ行く道を辿った。
本編序盤、デブラに対して「母親のことは覚えていない」と誤魔化していた。それは自分という存在さえ誤魔化し、否定している姿に見えた。しかし今回のヴァラクとの対峙を経て、母も自分も理由があって「普通と違った」のだと知る。神に与えられた力と向き合い悪を退けたことは、自分らしく生きるための礎になるだろう。
●アイリーンの不思議な力
アイリーンが持つ不思議な力の秘密は彼女の御先祖にあった。
ヴァラク、神への叛逆の罰としてor堕天使と見なされて神に力を奪われた
↓
ルチアという少女が代わりにその力を与えられた
↓
信心深いキリスト教徒だったルチア、拷問を受ける(当時はキリスト教の迫害があった)
↓
不思議な力に守られていたルチアへの最終手段として目玉がえぐり出された
↓
ルチアの目玉は聖遺物として力を持っているので、子孫が隠した
そのルチアの末裔が、アイリーンなのだ。だからこそ、火あぶりの幻覚にも負けずに、ヴァラクを返り討ちに出来たのである。筋書きだけ見るとヴァラクは、力を奪われ、その力によって追い払われる、なんともみっともない悪魔に思えてきた。
●ヴァラクとの因縁
ヴァラクは「ルチアの末裔は一人残らず駆逐してやる」という意気込みを表すかのように、聖遺物探しのヨーロッパ旅行をしながら、聖職者たちを殺しまくっていた。そしてようやく聖遺物に辿り着いたと思ったら、ルチアの末裔=アイリーンに阻止されるのだから、ざまぁ展開である。
モリースが寄宿学校に着いて以降は、モリースの異変を見た少年と、ローラン校長がヴァラクによって殺害された。少年はともかく、校長が殺された理由は分からない。校長の息子セドリックの霊をけしかけて殺すほどの理由があったように思えなかった。その直前にモリースが礼拝堂前に立っていたが、校長が声を掛けてその場を去ることになった。その流れから、聖遺物探しの邪魔になると判断したのかも知れない。或いは、単なる悪魔の戯れだろうか。何故かやたらとゴキブリと関連付けられるし、校長だけは本当に不憫。
少女ソフィーにも秘密がある?
●複雑な関係
ソフィーは教師ケイトの娘である。それが直接の要因かは不明だが、クソガキクラスメートたちにいじめられている様子があった。一方、寄宿学校に来てからそこまで日が経っていないはずのモリースとは打ち解け、距離が近いようだった。独り身らしい母といい感じになって欲しいなという朧げな期待もあったと思うが、純粋に友人としてその存在が嬉しかったのだろう。
●“第六感”が垣間見える
明らかに霊力がある、とはされていないものの、普通の子どもと違うなと思わせる部分がいくつかあった。
・閉じ込められた礼拝堂でヴァラクとニアミス(モリースがそばにいたから出現)
・母の声の幻聴を辿ったらヴァラクの姿(この時点で唯一シスター姿のヴァラクを見た存在)
・「この学校にはいちゃいけない何かがいる」と誰よりも早く感じ取る
・ステンドグラスのヤギに心底恐怖を感じる(その後実際悪魔が出没)
・ソフィーが握りしめた聖遺物入りの小箱が発光する
小箱の発光に関しては、「霊的な力をもつ者が手にして、悪魔の存在が近づいた時に、光り出す」可能性がある。アイリーンが小箱を掘り出して拾った時も、アイリーンがソフィーから受け取った時も発光していなかった。単純に悪魔に反応して自動発光するなら、もっとずっと光り続けるはずなので、悪魔の存在×手にした人間の組み合わせが発光条件と考えらえる。
死霊館ユニバース:アイリーンとヴァラクの深みが増す第二弾
各作品の事件の時系列としては下表①、映画公開順では下表②の通りである。
シリーズ第二弾にして、シスター・アイリーンの不思議な力の秘密が明かされる本作。また、作中の描写によって死霊館に登場するロレイン・ウォーレンとの関係性も示唆された。なお、ロレインとアイリーンを演じるのはファーミガ姉妹である。
| ①時系列順 | ②映画公開順 |
|---|---|
| 1952年 死霊館のシスター | 2013年 死霊館 |
| 1955年 アナベル 死霊人形の誕生 | 2014年 アナベル 死霊館の人形 |
| 1956年 死霊館のシスター 呪いの秘密 | 2016年 死霊館 エンフィールド事件 |
| 1967年 アナベル 死霊館の人形 | 2017年 アナベル 死霊人形の誕生 |
| 1969年 アナベル 死霊博物館 | 2018年 死霊館のシスター |
| 1971年 死霊館 | 2019年 アナベル 死霊博物館 |
| 1977年 死霊館 エンフィールド事件 | 2021年 死霊館 悪魔のせいなら、無罪 |
| 1981年 死霊館 悪魔のせいなら、無罪 | 2023年 死霊館のシスター 呪いの秘密 |
| 1986年 死霊館 最後の儀式 | 2025年 死霊館 最後の儀式 |
死霊館全体のまとめレビューはこちら➡【2026最新】死霊館ユニバース全作紹介!【シリーズ解説&見る順】
感想
前作同様、直接対峙する派手なアクションシーンは最後の最後まで出て来ない。それでも隠せないのが明らかにアップしたヴァラクの戦闘力である。ルーマニアでの事件後、西に進みながらばったばったと聖職者を死に追い込んできたらしいが、それによって力を蓄えたということなのだろうか。或いは、モリースという器を得て外に出たことで本領を発揮しているだけで、そもそもあれほどの強さを持っていたのかも知れない。死霊館シリーズではあまり強さが分からなかったが、舐めててゴメン。
モブと大差ない露出ではあるが、いじめっ子たちにはなかなかイライラした。特にボス的存在シモーヌは、虫を捕まえさせておいて「手間取ったわね」などと言い捨てる。性格捻じれ過ぎだろう。ソフィーを礼拝堂へ閉じ込めるというイジメ自体に加え、ソフィーが出て来てからの、ほ~ら、ボーイフレンドが助けにきた~みたいな言い方も、あの年齢の女子らしいものではあるが腹立たしい。このイジメのシークエンスは、後に聖遺物が埋められた場所を特定するための伏線的役割も持ってはいるのだが、それで許されると思うなよ、という気持ちである。だからシモーヌが悪魔のせいで負傷したところで、因果応報感もあり、たいして同情出来なかった。虫とクソガキは嫌い。
基本情報
【公開年】2023年
【監督】マイケル・チャベス
【キャスト】タイッサ・ファーミガ、ジョナ・ブロケ、ストーム・リード、アナ・ポップルウェル、ケイトリン・ローズ・ダウニー、ボニー・アーロンズ
【登場人物】アイリーン(シスター)、モリース(寄宿学校使用人)、デブラ(シスター)、ケイト(教師)、ソフィー(学生/ケイトの娘)、ヴァラク
【ポストクレジット】なし(ミッドクレジットあり)



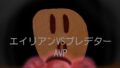


コメント