
プレデター犬って、200犬種あんねん
事実関係・疑問点の整理:新設定から新プレデターまで
異種交配するという新たな設定
●落とし物を拾う、ベタなスタート
本作は俺TUEE系主人公、スナイパーのクイン・マッケナが異星人=プレデターが落とした物を勝手に拾ってなんやかんやで息子の手に渡ってしまい、落とし主とか、落とし主を研究する組織とか、落とし物を狙う別の異星人から親子共々狙われることになって、もー大変!というのが大まかなストーリーである。
●プレデターの目的は、ベタじゃない
落とし物を狙う側のプレデターについては、襲来の目的が過去作であった「ただの狩り」または「成人の儀式のための狩り」とは異なることが後半明かされる。「進化のために人間の脊椎(髄液)を奪う」目的で地球にやってきた、となって侵略の色が加わったのだ。背骨から頭蓋骨までを持ち帰るのも、トロフィーとしてイケてるパーツだからではなく、遺伝情報をぶっこ抜く目的もあると改変された。
●設定変更による、思想変更
「その星で一番強い生物から脊椎を奪って遺伝的変化・進化を繰り返す」のは、これまでの“己の強さ”にストイックなプレデターたちとは相いれないはずだ。わざわざ地球まできて、プレデターより全般的に劣っているだろう人間を狙うのも謎である。しかし、プレデターと言っても様々な種類・クランがあるので、突飛な思想の集団が出現することもあるのだろう。
●上位種の存在
新設定により、「遺伝子改良で生まれた上位種」という概念も誕生。それがアサシンプレデターだが、わざわざオリジナル系統のプレデターと戦わせることでしょっぱい戦闘力インフレを見せ付ける。その後人間に負けるのだから、滑稽な話だ。
プレデターの狙い、自閉症のローリー
●ローリーという少年
今回プレデターが遺伝子情報を狙った対象は、クインの息子ローリー。彼は自閉症であると示唆されている。感覚が過敏であることと(警報に耳を塞いで座り込む)、サヴァン症候群的特性(瞬間的にチェスの盤面を記憶)が描写されていた。体格などフィジカル面では平均かそれ以下と思われる。
●ローリーが狙われた理由
プレデターのマスクやガントレットに組み込まれた情報を瞬時に解読したことで比類なき頭脳の持ち主だと判明したから……程度の描写しかなかった。「マッケナ狙ってます」「やっぱり俺チャン狙いか」「お前じゃなくて息子な」「ナンダッテー!」という茶番どんでん返しがしたかっただけ、とも思える合理性のない人選だった。
●自閉症の描き方
序盤では校内の警報音ですら耳を塞いでいたのに、ドンパチの戦闘中は特に取り乱すこともなかった。むしろ大人もびっくりの冷静さと判断力で素早く動き、助けになっていた。そんな一貫性のなさは、ローリーというキャラクターの理解を難しくさせるし、プレデターが彼を狙う根拠も曖昧にさせた。IQ200の超天才児だけどクソ生意気で大人たちは手がつけられない、みたいな設定にした方がまだマシだったかも知れない。
今回のプレデターたち:フジティブ、アサシン
●フジティブプレデター
見た目はクラシカルなタイプ。“プレデターキラー”という、人類がプレデターに対抗するための武器を渡すべく地球を訪れるも、別の宇宙船から攻撃を受けて墜落。スターゲイザーの研究施設から逃走する際、落ちていたライフルを手に取って発砲する=プレデターが人間の武器を使う、という、目新しい行動を取る。施設からの逃亡中に、切断された兵士の腕をサムズアップさせてヒョイと出してみせたのは、若干滑っていた。フジティブプレデターの人間社会への造形の深さを描きたいなら、別の見せ方をして欲しかった。人間と意思疎通出来た、と思った矢先、アサシンに簡単に殺されてしまう悲しい運命である。
●アサシンプレデター
アルティメットプレデター、アップグレードプレデターなどと呼ばれる。つよつよ生物の遺伝子をちゃんぽんした遺伝子組み換えプレデター。体格はこれまで登場したプレデターの中で最も大きく、ごつくて皮膚も厚く、リストブレードでの攻撃も無効化できる。プレデターキラーの回収と、裏切り者=フジティブプレデターの処刑が任務。フジティブを雑魚みたいに殺したり、突然翻訳機を使って上から目線の演説を始めたり、戦闘力は高いが可愛げゼロ。チートして戦闘力をインフレさせておいて、最後はクインに銃でやられる。
感想
これまでのプレデターの世界観と照らし合わせると、どうしてもコメディ色が強すぎて違和感を覚えた。どれだけ強いプレデターが現れても恐怖が感じられないし、登場人物たちの恐怖さえ伝わらなかった。
本作の監督シェーン・ブラックは、一作目のプレデターでホーキンスというシュワちゃんの部下を演じていた人物。作中でホーキンスは一人下品なギャグを言い続けるよく分からないキャラクターだったのだが、継承するなら「下品なギャグ」ではなくて別の要素にして欲しかった。
ご都合主義甚だしく、仲間たちは必要なくなった時点でどんどん雑に殺されていくが、主人公クインは不思議な力で守られ続ける。メキシコでフジティブプレデターと鉢合わせても、アサシンプレデターの前にしゃしゃり出ても、上空から宇宙船ごと落下しても死なない。主人公だから。
そもそもクインみたいなタイプは、嫌いに近い方の苦手なキャラだ。なんかすごい軍人らしいが、私書箱の料金を滞納して息子を危険に晒したり、出会って間もない得体の知れない男たちを家に連れ込んだり、いくらなんでも夫・父として行動に問題がある。フジティブプレデターが遺したプレデターキラーを見て、「俺の新しいスーツだ」などと宣う自信過剰っぷりにも辟易した。トニー・スタークが改良版のスーツを見て言うのとはわけが違う。フジティブプレデターも、別にお前に遺してないよ、と草葉の陰で泣いていると思う。
基本情報
【公開年】2018年
【監督】シェーン・ブラック
【キャスト】ボイド・ホルブルック、オリヴィア・マン、トレヴァンテ・ローズ、トーマス・ジェーン、キーガン=マイケル・キー、アルフィー・アレン、アウグスト・アギレラ、ジェイコブ・トレンブレイ、スターリング・K・ブラウン
【登場人物】クイン・マッケナ(米特殊部隊スナイパー)、ケイシー・ブラケット(進化生物学者)、ネブラスカ・ウィリアムズ(元空軍特殊部隊)、バクスリー(元海兵隊員)、コイル(元海兵隊員)、リンチ(元陸軍外人部隊隊員)、ネトルズ(ヘリコプターの操縦士)、ローリー・マッケナ(中学生/クインの息子)、ウィル・トレーガー(CIA/スターゲイザー責任者)
【ポストクレジット】なし

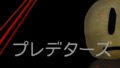
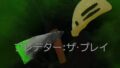
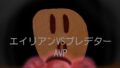


コメント